第4曲 アリア「わがすべての最たるもの」 変ロ長調、3/8拍子
4曲目は、テノール・弦楽器・通奏低音で演奏されます。弦楽器によるパスピエの冒頭でひときは美しい旋律が奏でられ、解放感にあふれた歓喜を表現しています。
なお、パスピエとは、17世紀から18世紀の古典舞曲で、ブルターニュに起源を発し、17世紀にパリで大流行した経緯があります。
「パスピエ」という語は、「通行する足」の意味であり、この舞曲に特徴的な軽やかなステップを言い表すものでした。
また古い時代は、8分の3拍子ないしは8分の6拍子の速い旋舞であり、先に触れたジグにも類似していたものと言われております。
歓喜から一変して、現世からの離別を告げるパートでは、何とも落ち着いた和やかな下降音による旋律が数小節ほど続けて奏でられており、その前の上昇音を主体にするテノール独唱とは相対象的に構成されている表現が、わかりやすく聴いて取れるのが印象的であると思われます。



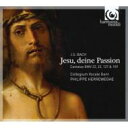


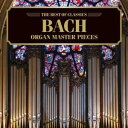


![【送料無料選択可!】【試聴できます!】J.S.バッハ: 作品集 [SHM-CD] [限定盤] / ヘルベルト・...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fneowing-r%2fcabinet%2fitem_img_317%2fuccg-9811.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fneowing-r%2fcabinet%2fitem_img_317%2fuccg-9811.jpg%3f_ex%3d80x80)




