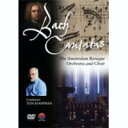バッハは、宗教カンタータ、世俗カンタータの両方を作曲しております。以下にバッハのカンタータをシュミーダーBWVの番号順に記載します。まずは、宗教カンタータBWV1 ~BWV25となります。
(宗教カンタータ1)
1.「輝く曙の明星のいと美しきかな」BWV.1、
2.「ああ神よ、天よりみそなわし」BWV.2
3.「ああ神よ、いかに多き胸の悩み」BWV.3、
4.「キリストは死の縄目につながれたり」BWV.4
5.「われはいずこに逃れゆくべき」BWV.5、
6.「われらと共に留まりたまえ」BWV.6
7.「われらの主キリスト、ヨルダンの川に来たり」BWV.7、
8.「いと尊き御神よ、いつわれは死なん」BWV.8
9.「救い主はわれらに来たれり」BWV.9、
10.「わがこころは主をあがめ」BWV.10
11.「神をそのもろもろの国にて頌めよ」BWV.11、
12.「泣き、嘆き、憂い、おののき」BWV.12
13.「わがため息、わが涙は」BWV.13、
14.「神もしこの時われらと共にいまさずは」BWV.14
15.「そは汝わが魂を陰府に」BWV.15、
16.「主なる神よ、汝をわれらは讃えまつらん」BWV.16
17.「感謝の供えものを献ぐる者はわれを讃う」BWV.17、
18.「天より雨くだりて雪おちて」BWV.18、
19.「かくて戦い起れり」BWV.19、
20.「おお永遠、そは雷のことば」BWV.20
21.「わがうちに憂いは満ちぬBWV.21、
22.「イエス十二弟子を召寄せて」BWV.22
23.「汝まことの神にしてダビデの子よ」BWV.23、
24.「まじりけなき心」BWV.24
25.「汝の怒りによりて」BWV.25、
以後、上記カンタータの中から、代表して第4番と第22番について紹介していきたいと思います。