第6曲「パルティータ第3番ホ長調」BWV.1006(その8)
第6曲「パルティータ第3番ホ長調」BWV.1006は、話題豊富な曲でもあるので、前回に続いて
もう少々触れてみたいと思います。
この曲の、第1楽章のプレリュードと第3楽章のガボットとロンドは、リサイタルなどでは単独で演奏される機会がよくある程の曲で、バッハの作品であることを知らなくても、誰もがどこかで耳にしたことのある曲の1つであるとの印象を持つことでしょう。
バッハ自信もこの曲のできの良さに満足していたのか、BWV.1006aにてリュートあるいはハープによる変奏曲を創作しているのです。
個人的に興味深いのは、第6楽章のジグです。
ジグは、このような組曲では終曲に配置するのが一般的でメジャーな手法であるのです。
この点、バッハも敢えてこのような流行を取り入れているところにも意外性を感じ取ることができます。
ジグは、元々は早いテンポのフランス風潮の影響を受けたフーガの技法で、曲の締めくくりには最適であるものとバッハ自信も共感していたものと思われます。
ここでの演奏は、ギドン=クレーメル(1947年、ラトビア(旧ソビエト連邦)出身の希に見る巧みな技巧能力を持つ名バイオリニスト)、イツァーク=パールマンの双方で甲乙つけがたいので、双方で聴き比べてみることをお薦めします。
![【20%OFF】[CD] ギドン・クレーメル(Vn)/SUPER BEST 100 5: J.S.バッハ: 無伴奏ヴァイオリ...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fguruguru-ds%2fcabinet%2f619%2fuccp-7005.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fguruguru-ds%2fcabinet%2f619%2fuccp-7005.jpg%3f_ex%3d80x80)
![[CD] イツァーク・パールマン(vn)/J.S.バッハ 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ&パルティ...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fguruguru-ds2nd%2fcabinet%2f327%2ftoce-14186.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fguruguru-ds2nd%2fcabinet%2f327%2ftoce-14186.jpg%3f_ex%3d80x80)











![【送料無料選択可!】【試聴できます!】J.S.バッハ: ヴァイオリン協奏曲集 [SHM-CD] [初回限定...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fneowing-r%2fcabinet%2fitem_img_356%2fuccp-9635.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fneowing-r%2fcabinet%2fitem_img_356%2fuccp-9635.jpg%3f_ex%3d80x80)




![即日発送可楽譜:バッハ:ブランデンブルグ協奏曲(全曲) [pocket score]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbremen-netshop%2fcabinet%2fjapanmusic%2fjapanscore%2fimg57946009.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbremen-netshop%2fcabinet%2fjapanmusic%2fjapanscore%2fimg57946009.jpg%3f_ex%3d80x80)



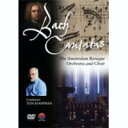
![【送料無料選択可!】【試聴できます!】ベスト・オブ・バッハ [生産限定盤] / クラシックオム...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fneowing-r%2fcabinet%2fitem_img_387%2fwpcs-12296.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fneowing-r%2fcabinet%2fitem_img_387%2fwpcs-12296.jpg%3f_ex%3d80x80)



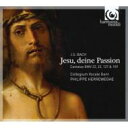


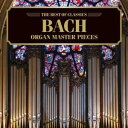


![【送料無料選択可!】【試聴できます!】J.S.バッハ: 作品集 [SHM-CD] [限定盤] / ヘルベルト・...](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fneowing-r%2fcabinet%2fitem_img_317%2fuccg-9811.jpg%3f_ex%3d128x128&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fneowing-r%2fcabinet%2fitem_img_317%2fuccg-9811.jpg%3f_ex%3d80x80)







